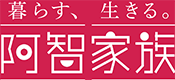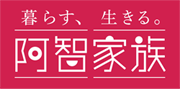本文
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)と経営発展支援事業
更新日:2023年10月10日更新
印刷ページ表示
制度の概要
経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、月12万5千円(年間150万円)を最長3年間交付します。
経営発展支援事業
新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、4分の3を支援します。
※複数の機械・施設等で申請可能ですが、50万円以上の機械・施設が対象となります。
交付の主な要件(すべて満たす必要があります)
独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
認定新規就農者となるには阿智村青年等就農計画認定委員会の認定を受ける必要があります。
独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
青年等就農計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
村の「目標地図」に位置づけられていること、または位置づけられることが確実であることがみこまれること
村が作成する「目標地図」または、「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実であると見込まれること。
前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(経営開始資金)
前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。
金融機関から融資を受けること(経営発展支援事業)
事前に金融機関に相談してください。
就農する地域の担い手として活動できること
- 地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力すること。
- 地域活動へ積極的に参加すること。
交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合
以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて100分の150を交付します。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦共に中心となる経営体として見込まれるよう規定されていること。
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
- 夫婦共に村の「目標地図」または「人・農地プラン」に位置づけられた者等となること、または、位置づけられることがみこまれること。
家族協定について
(注意)経営開始資金や経営発展支援事業申請者が家族協定を締結する場合、次の項目を協定に盛り込む必要があります
- 経営方針、役割分担(夫婦共同で決定する)
- 収益配分
- 夫婦が責任ある経営を共同で行う
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合
新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
交付の停止及び資金の返還について
以下等に該当する場合は交付停止となります。
- 交付対象者としての要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止または休止した場合
- 交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと判断される場合
- 耕作すべき農地の管理を怠りを遊休化させた場合
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
- 村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合
- 交付期間2年目が終了した時点で実施する中間評価でC評価(不良)と判断された場合
- 就農状況報告等が提出されない場合 など
以下に該当する場合は返還の対象となります。
- すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
- 資金の交付終了後、交付を受けた期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合
- 虚偽の申請をした場合
承認後の手続き等について
就農状況報告
交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出する必要があります。